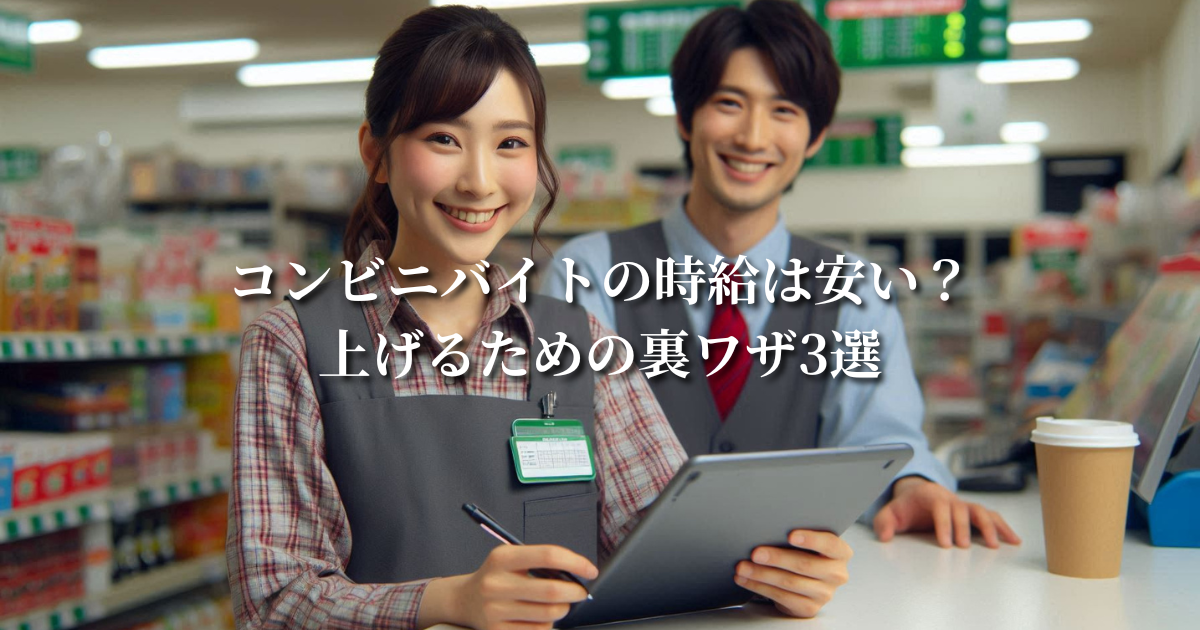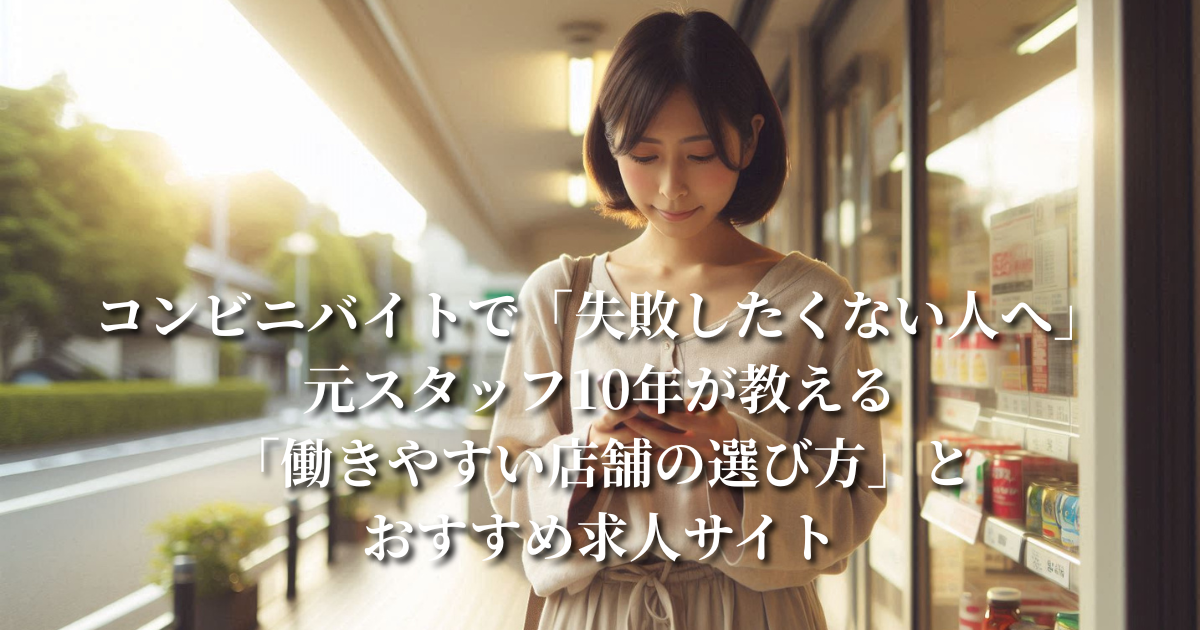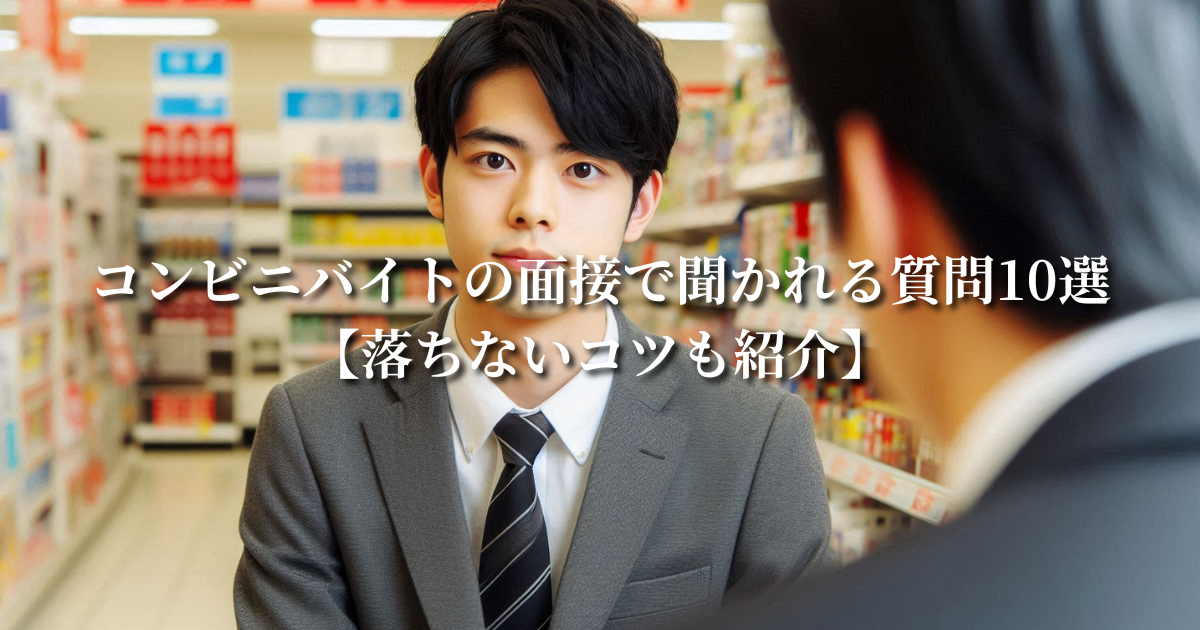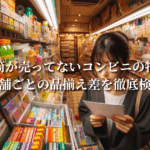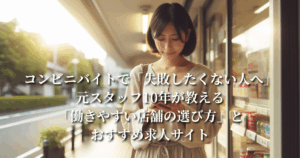コンビニ経営の成否を分ける最大の要素は「立地」です。
どんなにやる気があっても、立地を間違えると最初から赤字スタートになります。
逆に、場所が良ければ多少の経営ミスがあっても黒字を維持できるのが現実です。
年収を左右する「立地」の現実
筆者は元コンビニ店長として10年以上、複数店舗の経営を見てきました。
その中で感じたのは、「成功する店舗には共通点がある」ということ。
この記事では、現場と経営の両方を知る立場から、立地選びで失敗しないためのポイントを徹底解説します。
「人通り」よりも「目的のある動線」を見る
多くの人が誤解しているのが、「人通りが多ければ売れる」という考えです。
実際には、流れていく人より立ち寄る人が多いかどうかが重要。
たとえば駅前の通勤路沿いにある店舗でも、帰宅方向とは逆側にあるだけで来店率は大きく下がります。
また、大学や病院の近くなどは固定客がつきやすく、安定的な売上が見込めます。
チェックポイント
- 人が通るだけでなく立ち寄る理由があるか
- 駐車スペースが十分にあるか(車社会なら最重要)
- 競合店舗との距離は500m以内にどのくらいあるか
人の量ではなく、動線と目的を読むことが立地選びの第一歩です。
「昼と夜」「平日と休日」で客層が変わる
立地調査をする際は、1回の下見では不十分です。
同じ場所でも「時間帯」「曜日」で人の流れが全く違うからです。
昼はサラリーマン中心、夜は学生や帰宅客、休日は家族連れというように、時間によって売れ筋商品も変わります。
実際、筆者が担当した店舗では、昼間に売れていたお弁当より、夜間のホットスナックが利益率を押し上げたこともあります。
ポイント
- 昼と夜の交通量・来店者層をメモする
- 休日の利用者数もチェック(住宅地近くは特に)
- 周辺施設の営業時間も確認する(病院・学校・工場など)
一見良さそうな場所でも、夜間の人通りが途絶えるエリアでは深夜営業のコストが重くなり、人件費が赤字要因になることも少なくありません。
「競合」よりも「補完関係」で考える
隣に他チェーンのコンビニがあると「競合が多い」と思われがちですが、実はそれがチャンスになる場合もあります。
ポイントは、差別化できる立地かどうかです。
たとえば、A社が駅出口近くにあるなら、自分の店舗は駐車場付きで車利用者向けにする。
もしくは、イートインや宅配ニーズを取り込むなど、立地に応じたサービスで「選ばれる理由」を作ることができます。
実践アドバイス
- 同じ通りに複数の店舗がある=需要が多い証拠
- 競合を恐れるより、「誰をターゲットにするか」を明確に
- 商圏分析ツール(本部提供)を必ず活用する
フランチャイズ契約前には、本部が提供するデータ(人口密度・年齢層・交通量など)を鵜呑みにせず、自分の目で確認することが成功への近道です。
「初期費用」と「家賃バランス」を見誤らない
立地が良ければ家賃も高くなりますが、売上=利益ではありません。
実際、月売上1000万円でも、家賃が高ければ赤字になるケースは珍しくありません。
理想は、家賃が月売上の5〜7%以内に収まること。
それ以上だと人件費やロスが発生した際に一気に収支が悪化します。
チェック項目
- 家賃:売上比率をシミュレーションする
- 契約期間中に賃料が上がる可能性はないか
- 敷金・保証金・設備投資費を含めた総コストで見る
数字だけでなく、「固定費として支払い続けられるか」という視点で見ると、長期経営の安定性がわかります。
現場経験者の「感覚」を信じる
最後に一番大事なのは、机上のデータではなく現場感覚です。
筆者が見てきた成功オーナーの多くは、数字よりも人の動き・空気感を重視していました。
「この道は夜も明るい」
「車が止めやすい」
「近くに交番がある」
こうした細かな現場の感覚は、統計データには現れません。
オーナーが現場を歩いて得た感覚こそが、長期的な売上と安全性を左右する最強の情報源になります。
まとめ|立地選びは「データ×感覚」で判断せよ
コンビニ経営で失敗する多くの理由は、立地調査の甘さにあります。
人通り・家賃・競合などの表面的な情報だけで判断せず、時間帯・目的・ターゲット・動線まで考えることが、成功する店舗の共通点です。
「この立地なら勝てる」と思える根拠があるかどうか。
そこを曖昧にしたまま契約してしまうと、どんなに努力しても赤字から抜け出せません。
あなたがこれからコンビニオーナーを目指すなら、まずは1日中現地を歩き、車で回り、目で確かめること。
現場を知ることが最大の経営戦略です。