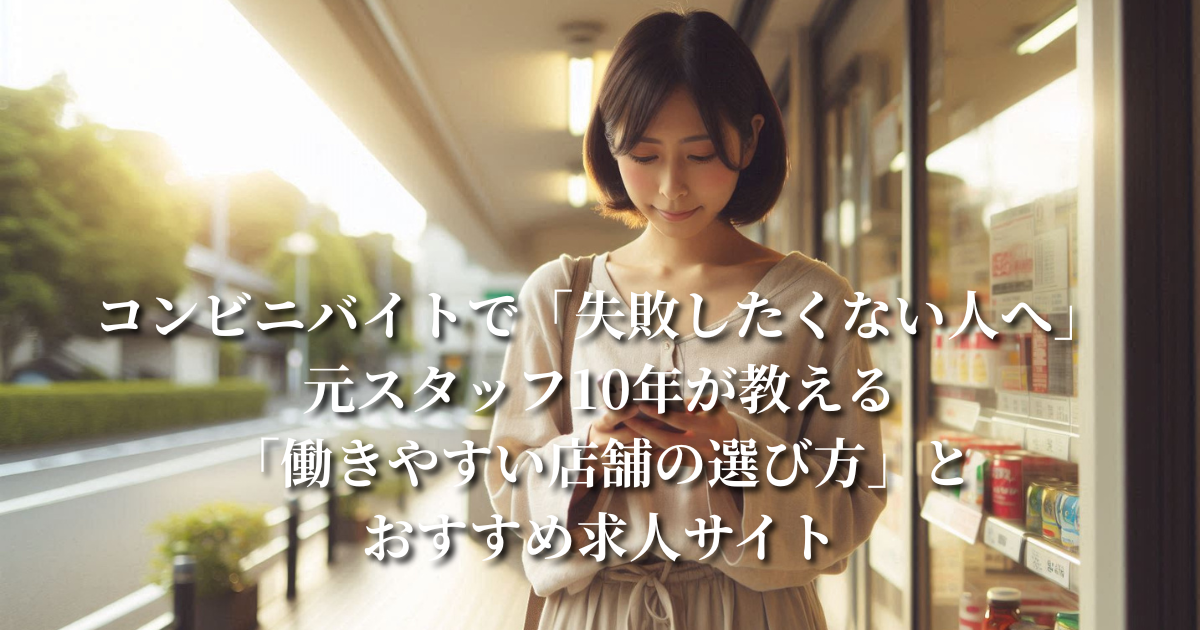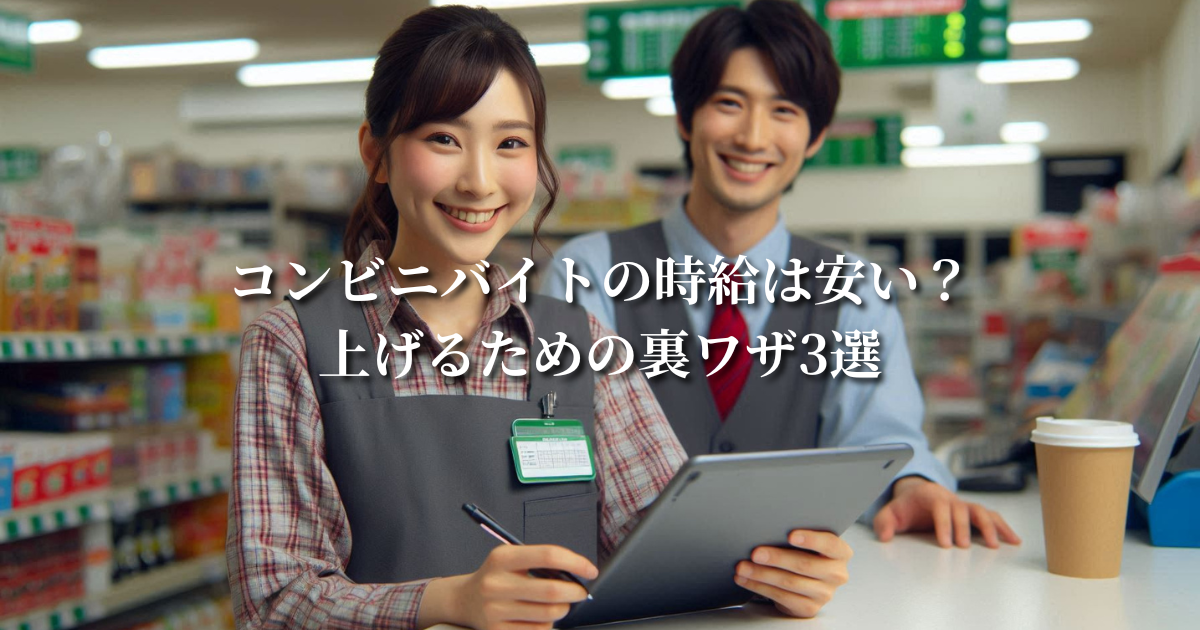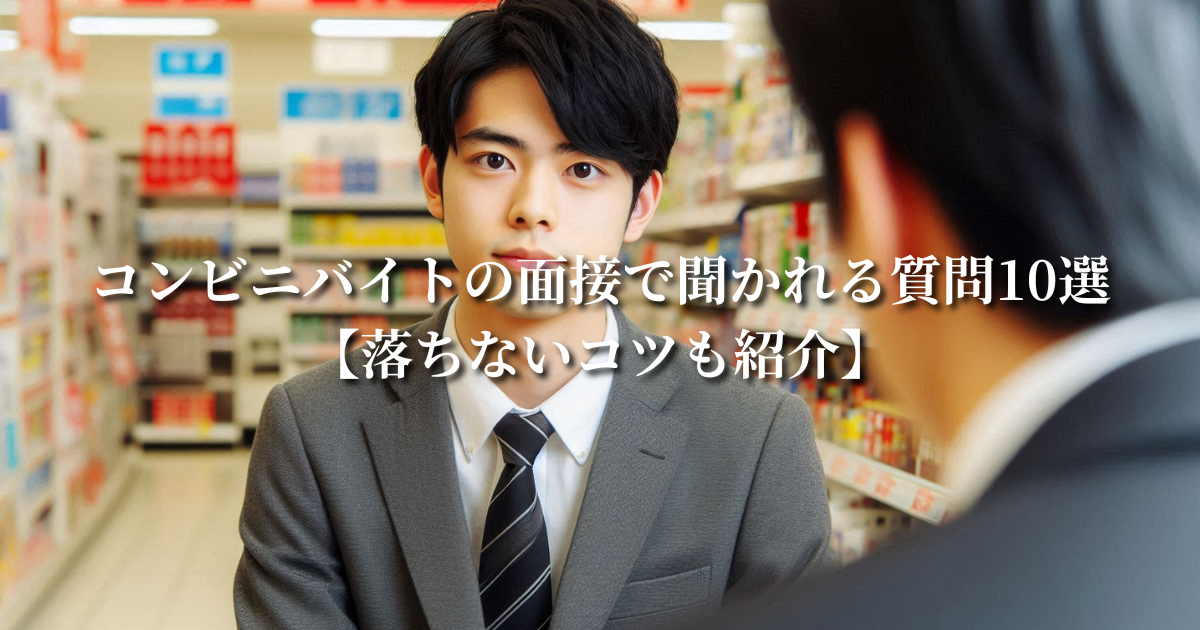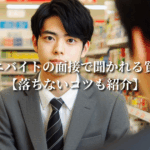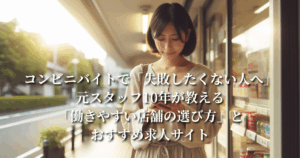スタッフ不足に悩むコンビニオーナー必見。
「求人を出しても人が来ない」
「シフトが埋まらない」
「休む暇がない」
こうした悩みを抱えるオーナーは年々増えています。
実際、私も現役時代に週7日勤務・睡眠3時間という地獄を経験しました。
しかし、そこから経営を立て直すために実践した5つの対策で、今では安定した店舗運営ができています。
この記事では、そのリアルな改善策をすべて公開します。
コンビニ業界の「人手不足」はなぜ深刻なのか?
まず前提として、人手不足の背景を整理しておきましょう。
- 少子高齢化で、若手のアルバイト層が激減
- 深夜勤務・低賃金など、敬遠されやすい職場環境
- SNSや口コミで「きつい仕事」というイメージが拡散
- 近隣店舗との人材争奪戦が激化
さらに近年は、24時間営業維持の難しさも加わり、現場は慢性的に疲弊しています。
結果として、オーナー自身がレジに立ち続ける「ワンオペ経営」に追い込まれるケースが増えています。
対策①:採用戦略を「時給」から「価値訴求」に変える
求人広告で「時給を上げる」だけでは、もう通用しません。
大事なのは、“働く意味”を伝える採用コピーです。
たとえば、
✖️「深夜時給1,200円」
⭕️「笑顔でお客さんを迎えるあなたが、この店の顔です」
このように「やりがい」や「温かさ」を打ち出すと、応募率は大きく変わります。
さらに、地元向け求人なら「地域密着」「家庭的な雰囲気」をキーワードに入れると◎。
対策②:スタッフ定着率を上げる「人間関係マネジメント」
採用しても辞めてしまう──これが一番のロスです。
辞める理由の多くは、「仕事がきつい」ではなく、「人間関係がつらい」。
現場では、オーナーや店長の一言が大きく影響します。
私が意識して変えたのは、次の3つです👇
- 出勤時に必ず名前で挨拶(「おはよう、〇〇さん!」)
- ミスを責めず、一緒に改善策を考える
- 1ヶ月に1回、雑談ベースのミーティングを開く
これだけで雰囲気が明るくなり、離職率が半分以下に下がりました。
結局、店を支えるのは「人」です。
設備投資より、人への気遣い投資のほうが効果的です。
対策③:業務を「仕組み化」して属人化を防ぐ
「この人がいないと店が回らない」──これは危険信号です。
人手が少ない時ほど、誰でもできるようにマニュアル化が必須。
- レジ操作・清掃・発注などを写真付きマニュアルに
- 新人研修は動画マニュアルを活用
- シフト表・発注表はクラウド共有(Googleスプレッドシートなど)
こうすることで、誰が入っても最低限の業務が回せます。
結果、教育コストの削減+安心感のある職場環境につながります。
店長としての実感
「属人化」はオーナーの精神的負担を倍増させます。逆に、仕組み化すれば「人がいない=終わり」ではなくなります。
対策④:外国人スタッフの採用とサポート体制づくり
今やコンビニ現場では、外国人スタッフが欠かせません。
しかし、「採用しても長く続かない」という声も多いです。
原因は、言語と文化の壁。
そこで私が実践したのは以下の工夫です。
- 業務マニュアルを英語・ベトナム語対応にする
- 日本人スタッフと外国人スタッフをペア勤務にする
- 日本語学校や地域支援団体と協力体制を築く
結果として、外国人スタッフの定着率が大きく上がり、
「この店は居心地がいい」
と口コミで人が集まるようになりました。
外国人が働きやすい店は、自然と人手不足に強い店になります。
対策⑤:時代に合わせた「業務削減」と「効率化」への投資
人を増やすのではなく、人に頼らなくても回る仕組みを作る。
これは、経営者の視点での次の一手です。
- セルフレジ・自動釣銭機の導入
- 発注システムのAI化(在庫の自動最適化)
- 廃棄管理のデジタル化(ロス削減)
初期投資はかかりますが、長期的な人件費削減とミス減少に繋がります。
現場の負担が減れば、スタッフの満足度も上がり、結果として定着率向上にも効果があります。
まとめ:人手不足は「工夫」と「仕組み」で乗り越えられる
| 課題 | 対策 |
|---|---|
| 採用できない | 採用コピーを“時給訴求”から“価値訴求”へ |
| 定着しない | 人間関係マネジメントで雰囲気改善 |
| 教育コストが高い | 写真・動画マニュアルで属人化を防ぐ |
| 外国人スタッフが続かない | 言語・文化サポートで定着率アップ |
| オーナーが疲弊 | 業務をデジタル化して負担軽減 |
人手不足を「経営の限界」と捉えるか、「改善のチャンス」と捉えるかで結果は大きく変わります。
現場を熟知しているオーナーだからこそ、現実的で柔軟な改革ができる。
それが、強い店舗に生まれ変わる第一歩です。